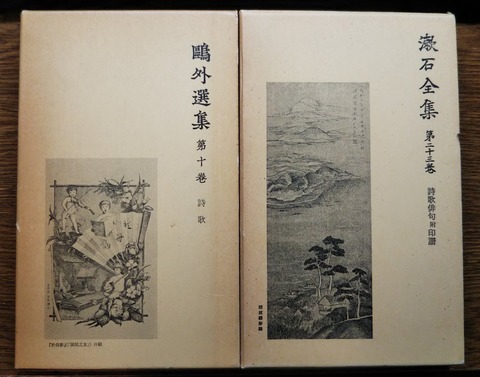
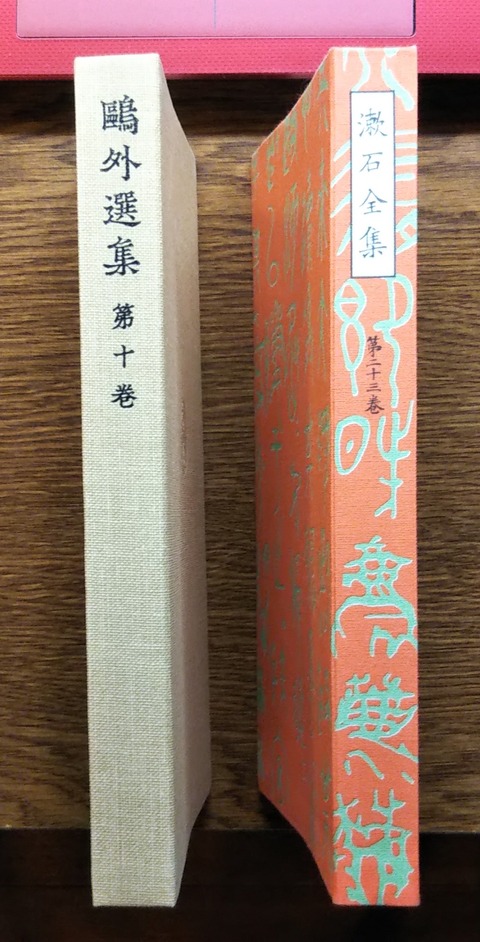 前記事の解答は…
前記事の解答は…森鷗外と夏目漱石。
岩波書店の
新書サイズ
選集と全集
1979*1981
年刊行版…。
画像四景で
二人共通の
詩の収録本
そう二人は
詩人として
も作品を残
した作家…。
短歌と俳句
同じ素材で
「鐘を撞く」。
大鐘をヤンキイ衝けりその音は
をかしかれども大きなる音
(鷗外・T11)
ごんと鳴る鐘をつきけり春の暮
(漱石・M32)
すべてに対照的な一首一句です。
鷗外は60歳最晩年の「奈良五十首」
からで…ヤンキイは下記Wikipedia*
にもあるように随伴したイギリス
皇太子御一行で…驚きの斬新さあり
大・大・音・音 惜しげもなく重複
大きな時代の変わり目の予感です。
漱石は31歳~32歳の熊本での俳句
結社**主宰になったばかり長女筆子
誕生の年…イギリス留学や作家活動
以前の句で…平明かつ手練れ感あり
オノマトペ(ごん)・切れ字(けり)・
季語(春の暮) ことごとくの月並み。
【イギリスに繋がる作家偲ぶ初夏】
[以下はWikipediaから抜粋]
* 鷗外の大正11年(1922年)
4月 - イギリス皇太子の正倉院参観に合わせ、奈良へ5度目の旅行。途中、いくどか病臥する。
6月29日 - 萎縮腎と診断される。また、肺結核の兆候も見られた。
7月6日 - 友人の賀古鶴所に遺言の代筆を頼む。
7月9日 - 午前7時死去。弘福寺(東京・向島)に埋葬される(翌年に三鷹の禅林寺へ)。
** 漱石の明治32年(1899年)
紫溟吟社(しめいぎんしゃ)は、明治時代に熊本県熊本市を拠点に活動した俳句結社 。1898年(明治31年)10月に、当時正岡子規、高浜虚子らと共に有力な俳人の一人で、第五高等学校教授を務めていた夏目漱石を主宰として、五高の学生であった寺田寅彦らの学生たちが興し、俳句の指導をする。同社は多くの俳人を輩出し、九州・熊本の俳壇に影響を与えた。
1899年(明治32年)5月 - 長女・筆子誕生。
1900年(明治33年)5月 - イギリスに留学(途上でパリ万国博覧会を訪問)。
1900年(明治33年)5月 - イギリスに留学(途上でパリ万国博覧会を訪問)。


コメント